合格者・内定者の声
渋谷区立保育士採用試験(公立)に合格しました!
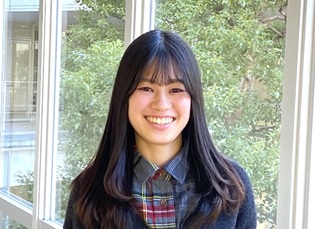 |
Q.1 なぜ、渋谷区(公立)の保育士を目指したのですか?
私が保育園へ通っていた時にお世話になった先生へ憧れをもち始めてからずっと保育士になることが夢でした。
憧れの先生のようになりたい、一緒に働きたいという夢があったことと、私が生まれ育った渋谷区で働きたいと思ったことから渋谷区の公立保育士を目指しました。
Q.2 どのように勉強をしましたか?
今年の試験内容は、一次試験が筆記と作文で、二次試験は面接でした。
作文の対策としては、まず過去に出題されたテーマで作文を書き、キャリアサポートセンターで添削や書き方の指導をしていただきました。
さらに「渋谷区の基本理念」や「どのような支援が行われているのか」などを調べ、実際に「渋谷区子育てネウボラ」に足を運んで見学に行くなどして、渋谷区の子育て支援への理解を深めました。
筆記試験の対策では、参考書を使って勉強し、保育所保育指針を読み込みました。
二次試験の面接対策では、想定される質問に対して自分なりの考えを準備し、先生方やキャリアサポートセンターの先生に面接練習をしていただきました。入退室や話し方などの動画を観て指導していただき、保育士になる上で必要なヒヤリハットや虐待などについての知識を教えていただきました。
Q.3 試験勉強以外にどのようなことに力を入れましたか? どのようなことが役に立ったと思いますか?
水泳インストラクターのアルバイトです。
幼児から児童を対象に水慣れや泳法の指導をしていく中で、子どもとたくさん関わることができ、けんかの仲裁の仕方や子どもたちが集中して話を聞けるような環境の整え方などを学ぶことができました。
視野を広くすることの大切さや、子ども主体で行動することの大切さなど、実習や今後に活かせることを学びました。
実習だけでなく、アルバイトやボランティアなどで子どもと関わることで様々なことが学べたり、知識を得ることができると思いました。
Q.4 試験当日はどのような様子でしたか?
一次試験、二次試験ともに、とても緊張しました。しかし、私なりに頑張ろうと思いながら落ち着かせていました。
一次試験の会場へは早めに到着し、参考書を読んで知識の確認をしていました。周りの受験者も参考書を読んでいる様子でした。
二次試験では、待ち時間に人事部の職員の方と一対一でお話をする機会がありました。渋谷区に関するアンケートを受けながら雑談などして、職員の方が緊張をほぐしてくださいました。
Q.5 保育実習の様子を教えてください。(楽しかったこと・苦労したこと)
実習では子どもたちとたくさん関わることができました。私は2歳児と4歳児のクラスで実習させていただき、2歳児はイヤイヤ期が重なっている子どもが多く、声掛けにとても苦労をしました。
そのような中、周りの先生方が不安なことや分からなかったこと等を聞いてくださる時間を毎日作ってくださり、相談することができたので、楽しい実習を行うことができました。
担当の先生が「子どもたちの年齢=子どもと保育士の距離」という言葉を教えてくださいました。2歳児と関わるならこぶし2つ分の距離を取りながら関わると、年齢に合った補助をできると教えていただき、実践しました。
Q.6 後輩へのメッセージをお願いします。
有短の先生方は最後まで全力でサポートしてくださいます。どんなに小さな悩みでも、相談してみるとたくさんのアドバイスをくださいます。
私は、実習や就活を行いながらアルバイトをして、友達と遊ぶ時間や趣味の時間をつくっている学生が充実感で輝いていると思っています。
大変で逃げ出したいこともたくさんあると思いますが、一人で抱え込まず、友達や有短の先生方に気軽に相談してみてください。そして、自分を信じて最後まで頑張ってください。応援しています。
私立幼稚園に内定しました!
 |
Q.1 なぜ、幼稚園教諭を目指したのですか?
妹やいとこなど周りに私より年下の子が多く、小さな頃から一緒に遊ぶことやお世話をすることが好きでした。
また、私が通っていた幼稚園の担任の先生は、いつも明るく笑顔で、ピアノが弾ける優しい先生だったので、私もこのような先生になって子どもたちの成長に携わりたいと思い目指しました。
Q.2 どのような就職活動をしましたか?
8月に川崎市の幼稚園・認定こども園の就職フェアに参加し、気になっている幼稚園に教育方針や行事などについて話を聞きに行きました。
保育実習の終了後、就職希望の幼稚園にお電話をして面接の日程を決め、10月の初旬に採用試験を受けました。試験の内容は簡単な作文とピアノ演奏と面接でした。
Q.3 試験勉強以外にどのようなことに力を入れましたか? どのようなことが役に立ったと思いますか?
事前準備としては、面接で答える内容と履歴書に力を入れました。履歴書はキャリアサポートセンターで繰り返し見ていただき、内容をまとめていきました。
また、履歴書の内容を深く面接で答えられるよう、家で何度も練習を行いました。さらに友人に相手になってもらい、自分の話の内容がおかしくないか聞いてもらっていました。
この2点に力を入れたため、面接当日はスムーズに答えることができました。
Q.4 試験当日はどのような様子でしたか?
試験は幼稚園で行われました。受験者は私と他大学の4年生の方の2人で、緊張をほぐすためにと先生がお茶を用意してくださいました。理事長・園長先生を含めた4名の先生方とお茶を飲みながら少し会話をして、緊張が解けてきたところで別室へ移動し、作文試験から始まりました。
作文試験はテーマが2つあり、45分ほどでした。その後、一人ずつピアノと面接が行われました。ピアノは自由曲を弾き、面接では「保育者という職の魅力」や「誰にも負けない強み」などについて答えました。
先生方が「普通に話すようにリラックスしてね」と声を掛けてくださり、少し緊張もほぐれ、面接を行うことができました。
Q.5 幼稚園実習の様子を教えてください。(楽しかったこと・苦労したこと)
初めての実習でずっと緊張していましたが、経験の場を増やそうと自分から「自己紹介のためのスケッチブックシアターをしたい」や「ピアノを弾きたい」、「読み聞かせをしたい」などと積極的に伝えると、先生方が褒めてくださりとても嬉しかったのを覚えています。
また、子どもたちが「明日も来る?」「今日は何組さん?」などたくさん聞いてくれたので、『実習を頑張ろう。子どもたちに会いに行こう』と思うことができました。
実習自体はとても楽しかったのですが、日誌は頑張って書いても抜けているところが多く、とても苦労しました。いつも2枚では収まらず、毎日3枚以上書いていても何かが抜けていて、直しを減らせるように細かく書くことを意識しました。その結果、最終日には「日誌が細かくよく書けている」と褒めていただけました。
Q.6 後輩へのメッセージをお願いします。
実習前はスケッチブックシアターやピアノ、手遊びなど、子どもの前でやれそうなことを準備し、初日からやりたいことをどんどん先生に伝えることで、自分の経験を積むことができ、先生にもやる気を伝えることができます。
また、前に立つことに慣れておくと責任実習の際に少し心に余裕が出てくるので、子どもの前に立つことはとても大事だと思います。子どもの前に出て失敗したとしても、日誌の反省部分に書けるので、「日誌のネタができた」と前向きに考えながらやってみると良いと思います。頑張ってください。
東京都小学校教員採用試験《大学推薦》に合格しました!
 |
Q.1 なぜ、東京都の小学校教諭を目指したのですか?
私が小学校教諭を目指した理由は、子どもたちの心の拠り所になりたいと考えたからです。
私が小学生の時の担任の先生は、どんな時でも親身に話を聞いてくださり、友達のことや日常の小さな悩みまで相談に乗ってくれました。また、休み時間や給食の時間にはくだらない話で一緒に笑ったり、全力で遊んでくれたりしたことが今でも楽しい思い出として残っています。
その経験から自分自身が生まれ育った東京で、子どもたちにとってそんな存在になりたいと思うようになりました。
Q.2 どのように勉強をしましたか?
一次試験の対策としては、毎週、キャリアサポートセンターの先生に参考書の課題と小論文の課題をいただき、それを基に毎日2時間程度、自宅で勉強しました。参考書では苦手な数学を重点的に取り組み、繰り返し復習することで理解できるよう努めました。
また、週に1度、先生に時間をいただき、参考書で理解が曖昧な部分の解説や小論文の添削をしていただきました。
日々の勉強と先生からのフィードバックを繰り返すことで、効果的に試験対策を進めることができました。
二次試験の面接対策では、夏季休業中に実施された大学での面接練習会に参加しました。10日間、先生方から回答の仕方や立ち居振る舞いなどの指導を受けることで、本番は自信をもって臨むことができました。
Q.3 試験勉強以外にどのようなことに力を入れましたか? どのようなことが役に立ったと思いますか?
自分自身の実践力を高めるために、子どもと関わる経験を積むことに力を入れました。
具体的には、放課後等デイサービスや小学校でのアルバイトを行い、実際の現場で子どもたちと接する機会を大切にしました。
そこで得た学びや気づきが、試験の論文や面接で具体的なエピソードとして活用することができました。また、教員として働く上で必要なコミュニケーション能力や子どものことを理解する力を身に付けることができました。
Q.4 試験当日はどのような様子でしたか?
一次試験では、広い会場に多くの受験生が集まっていました。運悪く、一番前の席だったので普段以上に緊張しました。また、周りの人たちが直前まで熱心に勉強している様子を見て、勉強道具を持っていなかった私はとても焦りを感じました。
二次試験では、会場や控室が比較的狭く、周りの受験生も緊張している様子が伝わってきました。しかし、その緊張感が逆に安心材料となり、「みんな同じ気持ちなんだ」と気持ちを落ち着かせることができました。
Q.5 教育実習の様子を教えてください。(楽しかったこと・苦労したこと)
楽しかったことは、子どもたちと遊んだり、話して笑い合ったりする中で、少しずつ絆が深まったことです。その絆のおかげで、研究授業の際には子どもたちが積極的に授業に参加してくれ、私を支えてくれたことがとても嬉しく、大きな励みになりました。
苦労したことは、研究授業の指導案作りです。一から指導案を作成するのは初めての経験で、限られた時間の中で完成させなければならなかったため、思うように進まず苦労しました。悩むことばかりでしたが、先生方のアドバイスもあり、何とか仕上げることができました。楽しい経験も苦労した経験も、私の成長に大きく繋がったと感じています。
Q.6 後輩へのメッセージをお願いします。
私は、自分自身の頑張りというよりも、有短の先生方やキャリサポートセンターの支えや協力のおかげで試験に合格することができたと思っています。
不安なことがあった時に助けを求めると、家族のように全力で支えてくれる心強い先生方がいるので、何もかも一人で抱え込まず、時には頼ってみるのもよいと思います。
また、小学校の教育実習はかけがえのない思い出になるので、小学校免許の取得を迷っている学生は、ぜひ行ってみてください。
東京都立特別支援学校 教員採用試験に合格しました!
 |
Q.1 なぜ、東京都の特別支援学校教諭を目指したのですか?
私には特別支援を必要としている人が身近にいることがきっかけで特別支援学校に興味をもちました。
小学校教諭の免許を取得するときに必須の「介護等体験」で特別支援学校に行き、実習をしました。
その際、特別支援学校で子どもたちと関わりたいと強く思うようになりました。
Q.2 どのように勉強をしましたか?
一次試験対策は、過去問を解いて、苦手な数学を集中的に個別指導していただきました。
苦手な教科を集中して勉強することで、点数を伸ばすことができました。
二次試験の面接対策は、大学で行われていた面接練習会に参加しました。面接時のマナーや本番を想定した質問などを練習することで、本番は緊張せずに自分の言葉で話すことができました。
Q.3 試験勉強以外にどのようなことに力を入れましたか? どのようなことが役に立ったと思いますか?
特別支援学校の子どもたちだけでなく、いろいろな子どもたちと関わることです。
私は保育士資格と幼稚園教諭の免許も取得するので、実習などを通して小学生以外の乳幼児とも関わってきました。
また、アルバイト先のお客様は家族連れも多く、子どもたちと積極的に関わりました。
あとは、何か一つでもいいので極めることが大事だと思います。私はアルバイトに全力を傾けてきたので、面接で話せることに繋がりました。
Q.4 試験当日はどのような様子でしたか?
一次試験では周りの受験生はテキストなどを持って、試験前ギリギリまで勉強している様子でした。
二次試験の面接の時は、会場に到着すると待合室に通されました。面接の順番が来るまで待つ間、資料などを使って最終確認をしていました。面接官は優しく話を聞いてくれる方だったので、緊張せず、思ったことを話すことができました。
Q.5 教育実習の様子を教えてください。(楽しかったこと・苦労したこと)
5年生と2週間過ごしましたが、子どもたちはとてもアクティブで、私は元気をもらいました。
研究授業まではあまり時間がありませんでしたが、担任の先生が丁寧に教えてくださったり、時間を作ってくださったりしたので、充実した2週間になりました。
研究授業当日も校長先生をはじめ他学年の先生方が見にきてくださり、細かいフィードバックをしてもらいとても勉強になりました。
なるべく早く名前を覚えて、子どもたちと休み時間にたくさん遊んでコミュニケーションを取ったことで、授業をスムーズに進めることに繋がったのだと思います。
苦労したことは特にありませんでした。
Q.6 後輩へのメッセージをお願いします。
何か一つだけでも頑張ることを決めると意味のある学校生活になると思います。
勉強でもボランティアでもいいですし、アルバイトでもいいと思います。大学生は勉強以外に楽しいことをたくさんできる期間です。時間を有効活用して、みなさんにも人生の中の素敵な時間にしてもらいたいです。
実習も挨拶など人として当たり前のことを当たり前にしていれば、大きな学びを得ることができます。学びたいという意欲を自分なりに理由をつけてみると、ただ過ごすだけでなく密な時間になります。
友達と支え合いながら、勉強、実習、楽しい時間を過ごしてほしいなと思います。楽しいことだけではないかもしれませんが、ぜひ何でも一生懸命に取り組んでみてください。